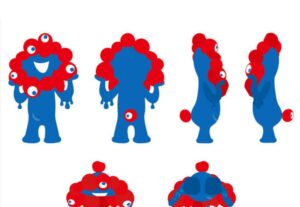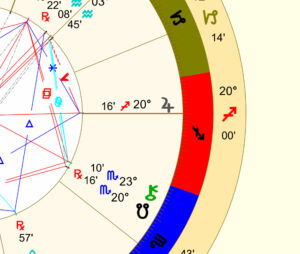こんにちは。広です。
毎日暑いですね🫠
暑いこの時期に、さらに乾いた人々の群像劇はいかがですか![]()
![]()
![]()


人が生きていくには水は不可欠です。
そして単純に生存という問題をクリアしても、
人間らしく生きて行くには水のスート(愛・感情)が必要になります。
けれどこの映画は、もう何年も何年も、水(愛・感情)が渇枯し続けている人びと、それも家族やごく身近な人間関係が地続きに総じて渇枯している人々のお話です。
彼らの現実生活(マルクト)は大地というより砂のように脆く
少しの風にもさらわれ、
水も蓄えることができず流されていく。
漂っていく。
ああ、それって、本当にそうだなと思います。
水(愛・感情)が渇枯し続けていると、
自力で自分の中(大地)に水(愛・感情)を保つ事が出来ないので
カラカラの大地に何も芽吹いたり根付いたりすることがないし、
少しの風(情報や意見)にも簡単にさらわれてしまう。
そんな日々をただ無為に繰り返している。
過去を手放せなくて前を向けずにいる。
または、1度も水(愛)を注がれたことがないから、どう前を向けばいいのかわからないでいる。
けれど、
それがダメなのかというと、そうでもなく。
喪失の念をただ感じる期間は必要なものでもあります。
人によって、その出来事の深さによって、ただ喪に服する期間が短かったり長かったり、
それぞれあるのだと思います。
それを無理やりに理性や思考で結論付けなくてもいいのだと思います。
自分の外側の世界から引きこもって、涙も水も枯れ果てた時に、
雨は必ず降り出してきます。
それは自然の摂理で循環であります。
最初のうちは、豪雨に流されるだけでどうにも扱えなくても、
いつしかその雨を自分サイズに溜めて取り込む事ができるようになるのです。
そんな劇中の雨の水への対応の変化が1つの見所です。
そしてもう1つ、象徴的なシーンがあります。
骨を大きな包丁で砕いていくシーンです。
タロットではマルセイユ版の15.死神の方がわかりやすいですね。
もう役に立たなくなった古い自我を鎌で解体していくことと重なります。
それまでは、大切に自分の心のガードにしていた自我=骸骨の体の骨 を
一度解体し、新たに構築していくという象徴です。
結局のところ、劇的な何かがもたらされたわけでもないけれど、
この時期を迎えて再び水(愛・感情)を取り込みはじめ、
古い自我を壊していったのです。
確かに物理的に失ったものはもう2度と帰ってきません。
けれど、生きている限り、この世の中は循環しているし、
自分の中の小宇宙も循環している、それには理由などないのですね。
このお話の行方がハッピーエンドでもバッドエンドでもなく
ただ心の移行の時期を描いているというだけのことなのでしょうね。
人生の途中で何も結論づける必要もないのだから![]()
![]()
![]()
人はこうして長い喪に服す時期を越え、
形には見えねども心を満たしてくれ支えてくれていた愛や感情に気づく時がくるのでしょう(カップ6)。
そしてまた人は夢を見る(カップ7)。
その夢を永遠にしたいと願う、それがこの地球での魂の経験となるのだから。
とてもいい映画でした![]()
![]()
お読みいただきありがとうございました。
今日もよき1日をお過ごしください!